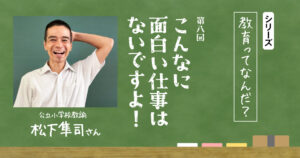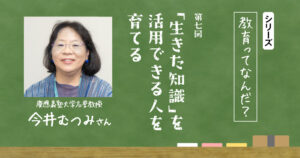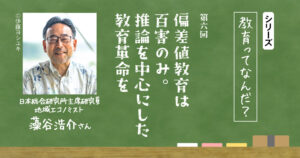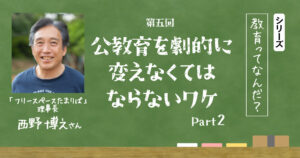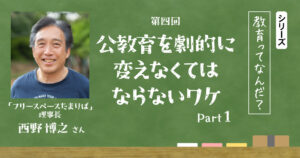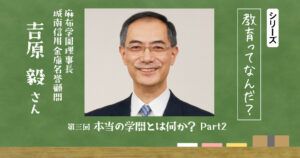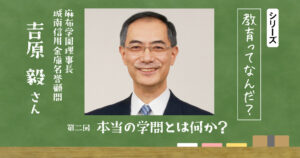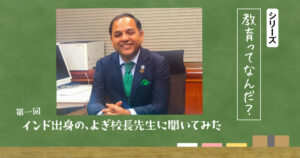子どもたちの個性を考慮しながら、成長を手助けし促す――これが教育の役目。そのためには子どもたちにとっていい授業をし、学びの場を雰囲気のいい空間とする先生の役割が非常に大きい。では、よき先生は、どう育つのか? 仕事についた当初から、よき職業人など存在しない。どの世界でも経験、年季が必要なのだ。即戦力、タイパなどという言葉が横行するが、本来、人の成長には手間と時間がかかるはず。多くの教員、また教員志望の学生たちと出会ってきた前田善仁さんに聞いた。
新任5年でベテランを求められる!?
――前田先生は小・中学校教諭の経験があり、現在は大学で学校教育学の教授として、教員志望の学生たちとも接していらっしゃいます。学校教育の現場にも詳しいと思いますが、まず教育現場の先生たちの現状はどうなっているのでしょうか?
現在は団塊の世代に続いて、団塊ジュニアの世代の先生方の退職が始まりつつあり、大量採用が必要とされる時代になりました。ところが教員採用試験は予想以上に低倍率化しています。すなわち教員になりたい人たちが減ってきているわけですね。それに拍車をかけるように「教員の仕事はブラックだ」「定額働かせ放題だ」と言われ、ますます教員のなり手が減っています。
一人前の教員になるには10年かかると言われていて、実際、いい先生になるには10年は必要なんです。ところが今はベテランの先生たちがごっそり抜けたこともあって、かつては若手とされていた5年目の先生が中堅として扱われ、〝ベテラン〟として教育現場に立たなければならなくなっています。ということは新任で来た人を5年でベテラン化させなければいけない時代になってきていると言い換えることができるかもしれません。
我々からすると「まだまだだな」と感じていても、若手教師を潰すわけにはいきませんから褒めて伸ばして、トラブルがあったときは尻拭いをする覚悟でいろいろと任せ、さまざまなポジションにも就かせているのが現状です。そんな時代になってきています。
――5年目でベテランですか……。担任もすぐに持つことになるのですか?
従前から新任でも持ちますが、今は確率が高くなっています。昭和の終り頃から初任者研修制度というのが始まったのですが、これは研修を受けてから教壇に立たせるのではなくて、教壇に立って担任の先生や教科担任をやりながら、月に1回とか2週間に1回とか、放課後3時からとか、小中高ともに都度都度で研修が入ってくるんです。要は実践しながら育てるかたちになっているんですね。
「教員は現場で育つ」「教員は現場で育てる」という言葉があります。教員の仕事や「よい授業」というものにマニュアルはなく、実践の中でつかみとっていくしかありませんし、若手教師は実践の中で育てていくしかない。だから一人前の教員になるには10年かかると言われているんです。
教育実習で変わる学生たち
――ところが10年も待っていられない状況になっている。教職志望の学生たちには、教師になったらすぐにクラスを持つよ、担任になるよといった意識づけが必要になりますね。
そうなのですが、学生たちと接していると、彼らとの温度差を感じますね。マニュアル的に教科書を読む、先生が渡すプリントに書いてあることを覚えればS評価をもらえる、そうした一方向的な講義形式の授業で知識を増やし、テストを受けて単位をもらってきていますから、そもそもノートをとるとか、聞いたことを要約しながら紙にメモする習慣が定着していない。どうしてもメモが必要なときはタブレットやスマホを出すという感じです。
4年生になると教育実習が入ってきます。4年になってからメモの活用力を伸ばすのでは遅いので3年生から準備に入るわけですけれど、「模擬授業はこういうふうにやります」と言っても、まったくメモをしないんです。「メモしなくて大丈夫?」と尋ねても、「大丈夫です。プリントはないんですか?」と。
教育実習に行ったら、メモも渡されないし、プリントもマニュアルもありません。職員朝会で校長先生や教頭先生が話した重要なことはメモするしかない。だからノートを用意して、大事なことは書き残しておかないと、教育実習のときに不手際を起こすことにつながりかねないと繰り返し伝えているのです。「採用されたら、いきなり教壇に立つことになるよ。でもマニュアルなんてないよ」と言っても学生たちはピンとこないようです。
――そうした学生たちも教育実習で変わりますか?
3年生には、教育実習が終わった4年生たちの話を聞いてもらっていますが、それが刺激になった学生は翌年の教育実習に備えて夏休みにちゃんと準備をします。3週間の教育実習中も4時間睡眠でがんばって、最後は児童・生徒たちから「行かないで」と言われて泣いて帰って来たという学生もたくさんいました。
そういう学生たちが教員採用試験に合格して4月に赴任していく。ひと月ぐらいして会うと、「教育実習はバイトの3倍ぐらいつらかった。その教育実習のつらさより、勤務してからこの一ヵ月間はもっとつらかった。でもきついけれど、やりがいは今のほうが大きいです」と笑顔で言うんです。教員はブラックだとか言われていますけれども、人を育てる教師の仕事はやっぱり、ものすごくやりがいがあるんですよ。
教師として成長していくには?
――つらさを感じながらも、やりがいや楽しさを実感し、何年もかかって本物の教師になっていく。けれども、いまの若手教員たちは5年でベテランになることが求められてしまう。不都合が起きたりはしないのでしょうか?
教える技術を持っているかどうかの試験は採用試験にはないですし、筆記試験で知識があるかどうかの篩[ふるい]をかけ、二次試験では面接などで、このような生徒がいたらどうするかとか、面と向かって話ができるかとかを見て合否を決めてはいる。とはいっても、低倍率ですから実際には実力が伴わない方が低倍率をかいくぐって教育現場に入ってきます。だから5年で、そのような方もきちんと実力を身につけ、後輩指導もできるようになってもらわないと、学校も困ってしまうし、新任も育っていかないということになります。
もちろん現場で育てていくシステムはあります。たとえば「研究授業」といって、ひとりの先生の授業を他の先生方が見学し、終了後に気づいたことをフィードバックする。ベテランの先生方からはベテランならではの視点でいろいろなことを指摘してもらえますし、授業力をあげて、いい授業ができるようにしていく校内研究のシステムがあるんです。
また、「現場でこの人をいい教師にしていくんだ」という思いから、ベテランの先輩教員が自分の授業を見せたり、若手がいつでも授業を見学できるように教室の後ろのドアを開けておいたり、生徒への声掛けを助言したりして、若い先生を育てることも行われています。
――教師として育っていく環境は用意されているわけですね。
いい授業を行うためには、いい学級経営が必要になります。生徒が安心して意見を言える心理的安全性が確保されていると、生徒同士が「その考えはスゴイ」と賞賛し合ったり、自然と拍手が湧きあがったりします。そうやって思いやりのある温かなクラスをつくっていくと、自由に意見を表明したり、考えを述べ合ったりできる雰囲気ができあがり、いい授業ができるようになっていくんですね。ただそこにはマニュアルはありません。クラスによって個性や色、クセはいろいろですから、マニュアルなんてものはあったとしても通用しない。
教師として成長していくには、いい授業を見て盗んで学ぶ、あるいはベテラン教師に「これを教えてください」「これはどうするんですか」と聞いてどんどん吸収していくこと、研究授業を嫌がらず、自分の授業に対するフィードバックをもらうことしかないんです。
マニュアル&スマホ世代ならではの伸び悩み
――それができれば教師として伸びていくことができる。一方で伸び悩む若手の先生もいるのでしょうか?
わからないことをベテランや先輩教師に聞くというコミュニケーションがあって、はじめてよい先生になる道筋の一歩が始まっていくのですが、なかには「聞けない」若手もいます。わからないことや困ったことがあると、放課後にひとりで「はあ~」とため息をついて思い悩んでしまう。
たとえば現役で教師をしているとき、6月の「学年だより」の作成を新任の先生に任せたことがありました。「管理職のチェックをもらいたいから、6月号を今日の放課後までにつくっていただけますか?」とお願いしたら、「はい」と答えるものの、放課後ずっとため息をついているんです。「どうしたの?」と尋ねたら、つくり方がわからないと。「わからなかったら聞いてね」と伝えていたのですが、私から「4月号と5月号のつくり方を見て学んで」と言われたことが頭に残っていて、「自分は学んでいないから聞けないと思ってしまった」と言うんですね。
――どうしてそんなことで思い悩んでしまうんですか!?
ひとつはマニュアル世代ということがあるでしょう。失敗もしたくないのだと思います。バイトでは、どんなバイトに行っても「できる」と褒められた。マニュアルもちゃんとあって、できないときは先輩がマニュアルに沿って教えてくれた。学校の先生も同じだろうと思ってしまったら、「ちゃんと教えてくれれば失敗しないのに、なんで教えてくれないんですか?」になります。わからないことは聞きつつ、教育実習でやった経験を活かしてこういうふうにやってみようという発想にはならないのかもしれません。
両隣に座っているベテランの先生が、「この授業でこのプリントを使うんだけど、使う?」と救いの手を差し伸べたり、「先生のクラスのリーダーになる子って、いま名簿に丸つけた子たちだから、この子たちに協力してもらえばうまくいくよ」とコツを教えてくれたりしていることにも気づかない。
――マニュアルを求めてしまうんですね……。
もうひとつはデジタルで育っていることです。とくに今はAIが進んでいて、スマホで調べれば瞬時に答えが得られてしまいます。しかも、非常にもっともらしい回答が出てきます。わからないことがあったら紙の辞書・辞典や百科事典をひく、知っていそうな人に聞いて教えてもらうなど、アナログのときは当たり前だったことが失われてしまいました。
辞書や百科事典を開くと、開いたページの他の文字や解説なども目に入ってきますから、プラスアルファで知識や情報が増えたりしていた。わからない漢字は画数で調べたり、部首別で調べたり、音訓読みで引いてみたりして読み方を探しました。いろいろな調べ方をすることで検索技術も身についていったわけです。それから、誰かに何かを教えてもらおうとしたら、まずはコミュニケーションが必要になります。相手が年配者であれば丁寧語をつかうとか、必ずお礼を言うといった配慮も必要になります。
ところがスマホで調べれば何でも一発でわかる時代に育っていることで、こうした経験をしないできている。アナログが培ってきた調べる能力、聞く能力、コミュニケーション能力が育っていないため、スマホに情報がないとどうしていいかわからなくなってしまうんです。
小中高からキャリア教育を
――教師になりたいと思って教師を目指し、教育実習で感動して、やりがいがあると思って入ってきているのに思い悩んでしまう。それで教師をやめてしまうようなことがあるのはもったいないですよね。それを止めるとしたら?
まずはキャリア教育を早いうちからやっておくといいのではないかと思います。キャリア教育というと、高校生の場合は「どの大学に行くか」「どの学部に行くか」になりがちだと思うのですが、教師になろうかなと考えて教育学部に進んだとして、途中から「自分は教師に向いていない」と思う人も出てくるかもしれないですよね。
小中高の時代に、どんな仕事があって、自分は何に向いているのかを調べて、多様な職業を考えてみるといった教育ができれば、本当に自分に向いている仕事、やりたいと思った仕事を見つけられるのではないかと思うんですよ。ですから給料が高いとか、かっこいいとか、ステータスがあるなどということではなく、やりがいや生きがいという視点から徹底して調べさせる。そうした経験を子どもたちにさせることが大事です。
――その職業にまつわるいろいろな世界を小中高のうちから知っておいたほうがいいということですね。先生になりたいなら、教職はどんな世界か、自分には合っているのか、そこに飛び込んでいったとき耐えられるのかを考えて進むかどうかを選ぶと。
教師になろうかな、教員免許を取ろうかなと思って勉強しているけれど、途中で「向いていないな」と思ったとき、キャリア教育でいろいろな仕事を調べたときのことを思い出して、別の職業を選択していくというのもありだと思うのです。人を育てることにやりがいを感じたいと思っているなら塾講師などの道もありますから。
情報を疑う、スマホを鵜吞みにしない教育も大事
それから、これは声を大にして言いたいのですが、「教育」ということを考えたとき、今はプログラミング能力とかデジタル技術の活用を重視した教育が小学校にまで入ってきています。この先の時代、AIやデジタルは不可欠でしょうが、デジタルの前にアナログで調べる技術やアナログで学ぶ、アナログでいろいろなアンテナを広げるといったことを子どもたちには経験させてほしい。
AIが出した情報を鵜吞みにしたり、スマホで調べた内容について疑うことをしなくなったりすると思考力が失われていきます。「アクセス件数が多い情報は信じていいんじゃないか」「有名な〇〇が語っていることだから信用できる」といったバイアスもかかりやすい。
たとえば新聞記事に「××県人は見栄っ張りな人が多いから貯蓄が少ない。だから老後は金銭的に困窮して自殺する人が多い」という大学教授のコメントが掲載されました。この記事を高校生150人に見せて信用できるかを尋ねたところ、「大学教授が言っているから信用できる」という回答が大半を占めました。このコメントが本当なのかを判断するには、見栄っ張り=貯蓄が少ないを証明する必要があるし、貯蓄の少なさと自殺の多さも関連づけなければいけません。ところが大学教授が言っているからというバイアスがかかって、多くの高校生が信じてしまう。
ビッグデータを活用したデータや情報も、「相関」はあるけれど、必ずしも「因果関係」があるとは限りません。「アイスクリームがたくさん売れると、水難事故の件数が増える。だから、アイスクリームには水難事故を誘発する成分が含まれている」のように、アイスクリームの売り上げと水難事故の件数は相関していたとしても、事故の件数とアイスクリームの成分には因果関係はまったくなかったりします。ですから「これ本当に信じていいの?」と疑うこと、出てきたデータは相関だけでなく因果関係も調べることが大事で、そうした教育を学校教育で行っていくべきですし、行えるのが教員だと思っています。
答えはなくても考え続けるトレーニングを
――わからなければ何でもAIに聞けばいい、スマホで調べればいいとなってしまうことの怖さというか、弊害というか。
AIをはじめとするデジタル技術が思考力やコミュニケーション力を奪っていると私は考えているんです。それを回避するには、答えはないけれど考え続けるトレーニングをする。それも学校教育の役割だと思うんです。
都内の中学校に出向いて、先生方の前で道徳の公開授業を行った際、子どもたちには、「君たちはこれから生まれ変わりますが、神様からはどこでどのように生まれ変わるかは選べないと言われています。戦争をやっているところに生まれる、貧しい家庭に生まれる、もしくは手足にハンディキャップを持って生まれる。それは選べないけれど、どんな社会にするかは決められます」と話して、どんなふうに生まれても困らない社会にするためのルールづくりをやってもらいました。
で、みんな一生懸命考えて、「どんな子もちゃんと平等に食べられるように、食料を配給制にすればいい」という答えが出てきたんです。そこで「この子はすごく汗水垂らしてたくさん収穫した。この子はずるくて、どうせ同じにもらえるからと少ししか働かなかった。同じでいいの?」と聞いたら、「ダメです。頑張った子には少し多くする」と言うので、「じゃあ、この子は片腕しかなくて力が弱くて1個しか収穫できなかった。この子も同じ量の配給でいいの?」と問いかけたんです。
残念ながら、そこでチャイムが鳴ってしまったのですが、1週間後に送ってもらった感想文の中に「家で親を巻き込んで考えても答えは出なかった。でも最低保障があるのはそういう理由からだと思います」というのがあって、本当にやってよかったと思いました。「子どもたちがこんなに深く考えているとは思いませんでした。答えがない道徳もありなんですね」という先生方からの感想もありました。
そのときは「ありきたりの道徳ではなく、今求められているのはこういう道徳なんです」と、現場の先生にわかってもらうために授業を見てもらったのですが、考えることを必要とする教育で、考え続けるトレーニングを受けて育ってきた子たちが増えていけば、考えさせる教育のできる先生も育ってきて、いい授業のできるいい教師が増えていくだろうと思います。
(了)
■聞き手・文 八木沢由香

まえだ・よしひと 神奈川県内の小学校教諭、中学校教諭、指導主事を経て、現職。専門は、理科教育学・理科教材学・生徒指導方法。広く教育問題の研究も行っている。編著『中学生・高校生のこころと特別活動』『わかる!生徒のこころと生徒指導』(東海大学出版部)ほか。